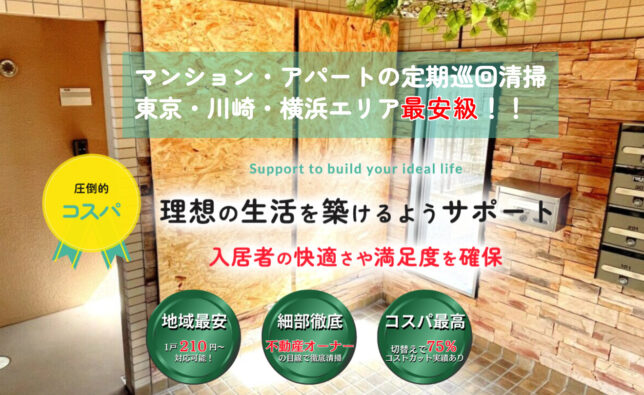登録日:2025.04.23
アパート経営を撤退する5つのタイミング!手続きの流れと再検討すべきケースも紹介

目次
「家賃収入が減っていて、このまま経営を続けて大丈夫?」
「築年数が経ち、建物の老朽化や維持費が増加してきた」
「家族に負担をかけず、資産を整理する方法はある?」
アパート経営は長期的な収益を得られますが、空室や修繕費などの負担が重なるなどの事情で、撤退を検討すべきタイミングも訪れます。そこでこの記事では、撤退するタイミングや手続きの流れに加えて、再検討すべきケースや集客力を高める方法も紹介します。
特に定年後の収入源としてアパート経営をしてきたものの、空室や物件の維持費の増加により不安を感じている方は、判断の材料としてぜひ参考にしてください。
アパート経営の撤退すべき5つのタイミング
アパート経営は長期的な視点で取り組むものですが、状況によっては手放すことも視野に入れる必要があります。経営が思うようにいかず、赤字やストレスが積み重なる前に、アパート経営を撤退するか判断しましょう。ここでは、アパート経営の撤退すべき5つのタイミングを紹介します。
1. 空室が増え、家賃収入が減少している
空室率が高くなり、家賃収入の減少が続いている場合は、アパート経営の見直しを考えるタイミングです。特に築年数の古いアパートでは、周辺に新築や設備の整った物件が増えると、相対的に選ばれにくくなる傾向があります。
家賃を下げても入居希望者が集まらず、募集広告の質や管理会社の対応が十分でないケースもあるため、状況が改善しにくいと感じる場面もあるでしょう。さらに収益の減少が続くと、修繕や管理にかけるコストや労力を最小限に抑えたくなる状況も出てきます。
その結果、物件の魅力がさらに低下し、空室が長期化する要因となります。状況を改善させにくいと感じる場合は、撤退も含めてアパート経営の方向性を改めて検討することが必要になるでしょう。
2. 修繕費・維持管理コストが増加している
築年数の古いアパートでは、修繕費や維持管理コストの増加が避けられません。入居者が退去するたびに発生する原状回復費用や、設備の入れ替えなどにかかる支出は多く、アパート経営の負担が増えていきます。
特に水回りや外壁などの老朽化は放置できず、大規模な修繕が必要になるケースもあります。仮にリフォームを行って最新の設備を導入したとしても、周辺の家賃相場とのバランスから、想定通りの家賃アップにつながらない場合もあるでしょう。
その結果、ローン返済や修繕費、維持管理コストを家賃収入で回収するのが難しくなり、投資として成立しなくなる恐れがあります。投資効率が悪い状態が続くようであれば、早めに撤退の可能性を検討することで、結果的に負担軽減につながります。
3. アパートの資産価値が下落し続けている
エリアによっては、アパートの資産価値が将来的に下がるリスクを抱えている場合もあります。全国的には不動産価格が高止まりしているとされていますが、人口減少が進む地域では事情が異なります。
空室が増えて賃料を維持できない状態が続くと、オーナーチェンジで売却を検討する場合には、収益還元の観点から物件の価格が下落しやすい傾向があります。築年数の経過に伴い老朽化による修繕コストが増してくると、買い手にとっての負担感も大きくなり、売却が難しくなるケースもあるでしょう。
周辺環境の変化や地域全体の不動産需要が低下している場合は、資産価値が大きく下がる前に動くことが、有利な撤退につながる可能性もあります。タイミングを見誤らないことが、損失を最小限に抑えるポイントとなります。
4. 入居者とのトラブルが増えている
入居者とのトラブルが重なると、アパート経営にかかる精神的な負担も徐々に大きくなっていきます。家賃の滞納やマナー違反といった問題が続くと、落ち着いて運営を続けるのが難しく感じるでしょう。管理会社に業務を委託していても、対応が後手に回れば状況は変わらず、他の入居者の退去につながる可能性もあります。
トラブルへの対応に時間や労力を割かれ、近隣住民との関係にも気を配る必要が出てくると、次第にモチベーションが下がってしまうかもしれません。こうした負担が積み重なり、経営を前向きに続けるのが難しいと感じる場合には、改めて今後の方針を検討することも考え方の1つです。
5. 相続や家族の事情で整理する必要がある
高齢のオーナーがアパート経営を続けているなかで、家族から「今後どうするのか」と相談される場面があります。年齢とともに管理の負担が増し、体力的に不安を感じることもあるでしょう。また、子どもが経営を引き継ぐ予定がない場合には、相続時の課題として残る可能性があります。
特に共有名義のアパートでは、親族間で意見が分かれることで、意思決定に時間がかかります。資産整理を円滑に進めるには、家族と話し合いながら、後継者を誰にするかを話し合い早めに方向性を決めておくと、将来的な不安を軽減する選択肢となるでしょう。
アパート経営を撤退するときの手順
経営を続けるのが難しくなったときには、撤退を視野に入れることも1つの判断です。しかし、撤退にはさまざまな手続きが伴い、思った以上に時間や労力がかかる場合もあります。
物件の売却価格の査定や入居者への通知など、手続きの内容を理解して進める必要があります。物件の状況やご自身の方針によって最適な対応は異なるので、あらかじめ流れを把握しておくことが大切です。ここでは、アパート経営を撤退するときの手順を紹介します。
1. アパートの市場価値を調査する
アパートを撤退する前に、まず現時点での物件の市場価値を把握しておくことが大切です。売却価格の目安を知ることで、今後の選択肢や売却後の収支の見通しが立てやすくなります。
複数の不動産会社に相談することで、相場より安く売却してしまうリスクも回避できます。将来の撤退を見据えて、物件の価値が落ちないうちに動けるかが、結果を左右するポイントとなります。
2. 入居者へ通知し立ち退き交渉を進める
アパートを解体し更地で売却する場合、入居者への通知と立ち退き交渉が必要になります。入居者への通知は原則として、6ヶ月以上前に行う必要があり、立ち退きは正当事由が求められます。場合によっては、入居者が立ち退きを拒否する可能性もあるため、丁寧な対応が必要です。
オーナーチェンジでの売却であれば、入居者はそのまま住み続けられるため、交渉は不要です。一方でアパートの解体が伴う場合では、すべての入居者に立ち退きを求める必要があります。
立ち退き料の相場は、家賃の6〜12ヶ月分程度かかる場合もあります。交渉が難航すると撤退時期に影響が出る可能性があるため、弁護士や専門家のサポートを活用するのが安心です。
3. 売却・解体・相続など撤退方法に合わせて手続きを進める
撤退方法によって必要な手続きは異なります。以下の表に、撤退方法ごとの手続き内容をまとめました。
| 撤退方法 | 手続き内容 |
| 売却の場合 | 不動産会社と媒介契約を結び、販売活動を開始する |
| 解体の場合 | 解体業者を選定し、近隣住民への通知や補助金の確認を行う |
| 相続の場合 | 家族と相談し、相続税の試算や遺言書の準備を進める |
いずれの撤退方法を選んでも不動産会社や司法書士など、各分野の専門家に相談することで、手続きの漏れやトラブルを防ぎやすくなります。所有権移転登記や契約書の締結など共通の作業も多いため、事前にスケジュールを整理することが重要です。
4. 撤退にかかる税金・費用を計算し、精算を行う
アパート経営からの撤退では、複数の費用や税金が発生します。実際に必要になる費用の項目と目安については、以下のとおりです。
| 項目 | 費用の目安 |
| 譲渡所得税・住民税 | 売却益に対して最大20~39%の税金が発生 |
| 売却時の仲介手数料 | アパート売却時に不動産会社へ支払う費用。以下のように法律で上限が設定されている。・200万円以下:売却価格の5%・200万円超〜400万円以下:売却価格の4%+2万円・400万円超:売却価格の3%+6万円※別途消費税がかかる※売買価格が800万円以下の空き家などは「30万円+消費税」が上限となる特例あり |
| 立ち退き料 | 家賃6~12か月分 |
| 解体費用 | 物件や地域により変動 |
| 登記・手続き費用 | 20万円〜 ※登録免許税は、物件価格や移転理由により変動 ※所有権移転・抵当権抹消・司法書士報酬など |
アパート経営を撤退するときは、合計で数十万〜数百万円の費用が必要になる可能性があります。税理士に依頼し、節税対策を含めた精算のシミュレーションを行っておきましょう。
アパート経営からの撤退を再検討すべきケース
アパート経営からの撤退を考える場面でも、アパートの価値や今後の収益改善の可能性によっては、経営の継続を再検討したほうがいいケースもあります。たとえば、建物の状態に問題がなければ、リフォームのような工夫次第で収益の改善につながる見込みもあるでしょう。
ここでは、経営改善の可能性が残されていると考えられる状況を紹介します。物件の特徴や対策によっては、収益を回復できる場合もあるため、撤退を決断する前に再検討することが大切です。
1. リフォームや設備投資でアパートの価値を高められる
アパートの構造や立地条件が良ければ、リフォームや設備の見直しによって収益性を改善できる可能性があります。たとえば、キッチンや浴室といった水回り設備を新調するだけでも、入居希望者の印象は大きく変わるでしょう。さらに大学や企業へ通える地域では、デザインを若年層向けに変更すると、反響の増加が期待できます。
築年数が経過していても、外観や室内の内装リフォームなどで住みやすさを演出すれば、競合物件との差別化が可能です。初期投資は必要ですが、中長期的に空室リスクを抑えられたり、家賃水準の回復が見込めたりするなら、撤退よりも継続を検討する価値はあるでしょう。
2. 空室対策をすれば入居率が改善する可能性がある
空室が長引いている場合でも、募集条件や情報の見せ方を見直すことで、反響が大きく変わる可能性があります。収支の都合を優先して家賃を設定していた場合は、近隣物件の相場を参考に調整することで、適正家賃に近づくため反響が増える可能性があります。
加えて、家具や家電を備えたプランや、一定期間家賃を無料にするフリーレントの活用は、単身者や転勤者の関心を引きやすくなります。さらに、物件の魅力がうまく伝わっていないケースも多く、管理会社任せの募集では十分な効果が得られないこともあります。そうした場合には、自ら広告されている内容を確認するのが有効です。
ECHOES(エコーズ)を使えば、SUUMO・HOME’S・at homeなどの大手ポータルサイトへ一括で物件を掲載可能。さらに、写真やコメント、間取り図をオーナー自身の手で編集・更新できるため、物件の魅力がしっかり伝わる情報発信が実現できます。撤退を考える前に、ECHOESを使って募集戦略を見直してみることも重要です。

アパート経営の撤退回避には入居者の募集活動改善が重要
アパート経営を続けるうえで、空室が長期化すると家賃収入が不安定になり、「このまま続けるべきか」と悩むこともあるかもしれません。しかし、問題の本質は“物件の力”ではなく“募集のやり方”にある場合も、入居が決まらないケースがあるため注意が必要です。
管理会社に任せきりになっていると、募集が行われていなかったり広告の質が低かったりと、管理会社の対応に課題があるケースも見られます。
こうした状況を改善するには、賃貸募集支援ツールであるECHOESのようなサービスを活用するのがおすすめです。ECHOESは、掲載後の閲覧数・問合せ数などの反響データを“見える化”し、改善すべきポイントが把握できるのが特長です。加えて、ECHOES独自の「反響改善アナライザー」では、過去の成約データと比較してどこが募集の問題点か自動で分析。管理会社に頼らずとも誰でも成約につながる募集が可能になります。募集活動の改善によって撤退を避けられる可能性もあるため、効果的に集客できるECHOESの活用をご検討ください。

まとめ:アパート経営の撤退が最善策か見直そう
アパート経営には空室や修繕費の増加など、判断に迷う状況もあるでしょう。ただ、撤退を決める前に収益改善の余地がないか、募集戦略の見直しを検討することも重要です。収益確保のために、集客力の強化が重要です。
ECHOESを活用すれば、ポータルサイトへの確実な掲載から、物件情報のブラッシュアップ、反響状況の分析まで、オーナー自身で成約率を高める“攻めの一手”を打てる環境が整います。撤退か継続かを見極める前に、まずはECHOESを活用して集客力強化を目指してみてはいかがでしょうか。