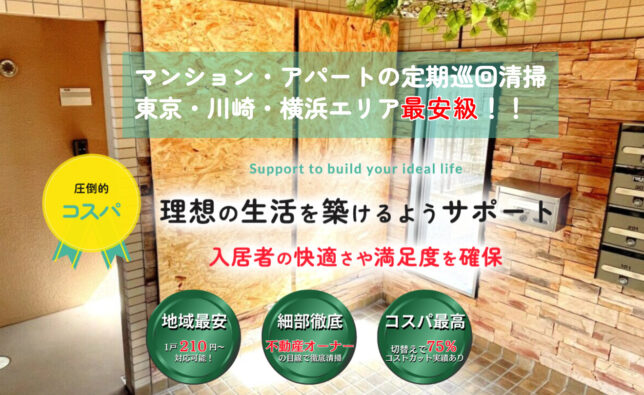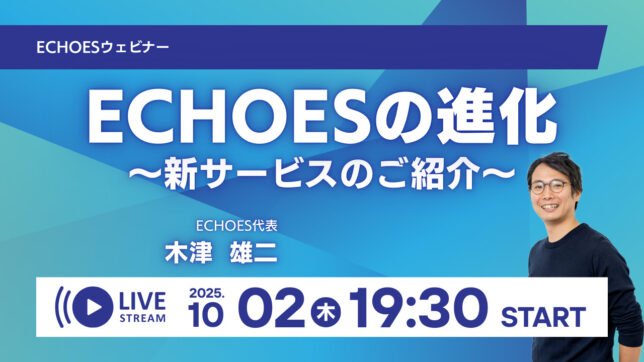登録日:2025.04.23
生活保護者向けのアパート経営がおすすめな3つの背景!想定されるリスクと回避策も紹介

目次
「生活保護受給者を受け入れることで空室を解消できる?」
「生活保護の『住宅扶助』があるとはいえ、本当に家賃はきちんと支払われるのか?」
「生活保護者向けのアパート経営は儲かる?」
近年は高齢者世帯が増加しており、生活保護受給者を入居対象としたアパート経営が注目されています。空室対策に悩むオーナーにとっては、新たなターゲットとして有力な選択肢となる可能性があります。
実際に生活保護受給者の多くは高齢者であり、賃貸契約を結ぶのが難しいケースが少なくありません。入居対象として生活保護受給者を受け入れることで、オーナーは安定した家賃収入を確保できるメリットがあります。
この記事では、生活保護者向けのアパート経営が有望な3つの理由を解説するとともに、考えられるリスクとその回避策について紹介します。空室対策に悩むオーナーの方は、ぜひ最後までご覧ください。
生活保護者向けのアパート経営がおすすめな3つの背景
アパート経営では入居率が重要であり、空室対策が欠かせません。ここでは、アパート経営における空室対策として「なぜ生活保護者を対象にするのが良いのか」を解説します。
- 生活保護者の入居ニーズが高まっている
近年、生活保護受給者のうち高齢者の割合が増加しています。厚生労働省の資料によると、生活保護を受給している世帯類型の割合は、以下のとおりです。
| 類型 | 世帯数と構成割合(令和6年11月) | 世帯数と構成割合(令和元年11月) | 世帯数と構成割合(平成26年11月) |
| 高齢者世帯 | 903,968世帯 55.0% | 897,003世帯 55.1% | 762,678世帯 47.5% |
| 母子世帯 | 62,471世帯 3.8% | 81,083世帯 5.0% | 108,971世帯 6.8% |
| 障害者・傷病者世帯 | 414,582世帯 25.2% | 408,318世帯 25.1% | 455,457世帯 28.3% |
| その他 | 260,102世帯 15.9% | 242,407世帯 14.9% | 279,404世帯 17.4% |
(参考:厚生労働省「生活保護の被保護者調査結果(R6.11、R1.11、H26.11)」)
直近10年を見ると、生活保護受給者全体の半分以上が高齢者世帯です。生活保護を受けている方は支払い能力を懸念して入居を断られることがあり、特に高齢者は契約が難しいと言われます。
今後も高齢化社会は継続する見込みであり、生活保護を受給している方の入居ニーズは高いと言えます。
- ターゲット層を絞ることで差別化できる
生活保護受給者の入居を受け入れることで、他の賃貸物件と差別化できます。多くのオーナーは、家賃滞納リスクや手続きの煩雑さを理由に生活保護受給者の入居を敬遠する傾向にあるからです。そのため、生活保護者向けアパートにはニーズがあり、空室を埋めやすい特徴があります。
生活保護受給者には、福祉事務所に所属するケースワーカーが担当者としてついているため、万が一の際には相談が可能で安心して賃貸できます。生活保護受給者を受け入れる物件は競争が少なく、安定した家賃収入が見込めて入居率を確保しやすいです。
- アパート改修に補助金が活用できる
住宅セーフティネット制度とは、高齢者や低所得者などの入居を拒まない賃貸住宅を支援する制度です。住宅セーフティネット制度を活用すれば、生活保護受給者向けに以下にあげる改修費用の一部を補助金でまかなえます。
- 耐震改修工事
- バリアフリー化工事
- 防音・遮音工事
住宅セーフティネット制度に登録した物件は、自治体や支援機関のサイトを通じて住宅確保要配慮者向けの物件として紹介されます。そのため、生活保護受給者をターゲットにした入居募集に有効です。補助金を活用すれば少ない費用負担で魅力的な物件に改修でき、入居率の向上にも繋がります。
生活保護者向けアパートの家賃収入が安定する3つの理由
生活保護者は一般の入居者とどのような違いがあるでしょうか?ここでは、生活保護者が入居すると家賃収入が安定する3つの理由を解説します。
- 生活保護受給者には住宅扶助がある
生活保護者向けのアパート経営では「住宅扶助」という制度を活用することで、家賃滞納のリスクを抑えられます。住宅扶助は生活保護を受給している方の家賃を自治体が補助する仕組みで、オーナーにとっては家賃収入の心配がありません。
賃貸契約時の敷金・礼金や更新料が住宅扶助の対象となる一方で、以下の内容は含まれない点は注意が必要です。
- 管理費
- 共益費
- 水道光熱費
住宅扶助の支給額は、地域の物価や家賃相場に応じて決められています。家賃の上限はあるものの、オーナーが住宅扶助の範囲内で家賃設定をすれば、確実に家賃収入を得られるため賃貸経営のリスクを抑えられます。
- 長期入居が見込める
生活保護受給者は一度住み始めると長期間にわたって入居する傾向が強いため、空室リスクを抑え安定した収益につながります。長期入居が期待できる理由は、以下の3点です。
- 入居できる物件が限られているため、次の物件を見つけにくい
- 引越し費用が自己負担のため、簡単に転居できない
- 住宅扶助には更新料が含まれており、更新が負担にならない
生活保護受給者は一般的な賃貸物件では入居を断られるケースが多く、一度入居すれば自ら積極的に引越しをする可能性は低いと言えます。転居費用が自己負担となるため、現在の住まいに留まる可能性が高いです。高齢の生活保護受給者は住み慣れた環境を変えたくない思いが強いため、一度入居すれば長期間の入居が期待できます。
- 家賃の交渉がほとんどない
生活保護受給者が住める物件の家賃は、住宅扶助の範囲内に収める必要があるため、上限を超える物件には原則住めません。生活保護受給者は、ケースワーカーから住宅扶助の上限内の賃貸物件に住むよう指導が入ります。そのため、家賃を安くしてもらうための交渉よりも、最初から住宅扶助内で契約できる物件を探す傾向があります。
また、家賃の支払いを怠ると福祉事務所から指導が入るため、生活保護者は家賃交渉よりも適正な物件を選ぶことを優先します。最終的に住宅扶助の範囲内の物件で契約するため、交渉の必要がありません。
生活保護者向けのアパートを経営する3つのリスク
生活保護者は募集しやすく空室を埋めやすい一方で、一般的な入居者とは異なるリスクがあります。ここでは、生活保護者が入居することで起こり得る3つのリスクを解説します。
- 入居までに時間がかかる
生活保護受給者は一般の賃貸契約と異なり、入居までに時間がかかります。生活保護受給者が物件を契約するには、ケースワーカーとのやり取りや役所の審査が必要になるため、スムーズに入居できるとは限りません。
ケースワーカーは、家賃が住宅扶助の上限額内で適正な条件かを精査します。敷金・礼金や更新料などの支払い手続きは、役所が書類を確認してからになるので、支給されるまで時間がかかります。
自治体の対応が遅い場合は入居までに1ヶ月以上かかるケースもあるため、オーナーは時間がかかることを理解しておく必要があります。
- 近隣とトラブルになる可能性がある
生活保護受給者は他の入居者と生活習慣や行動パターンに違いがあり、近隣住民との間でトラブルが発生するリスクがあります。特に高齢者の場合、外出の機会が少なく室内で過ごす時間が長いです。
そのため、生活音やテレビの音などが長時間にわたり近隣に影響を与える可能性があります。精神的な病状を抱えている場合は、幻聴や過敏な反応で小さな音にも過剰に反応するクレームや苦情が考えられます。
近隣とのトラブルが深刻化すると、他の入居者が退去し空室が増える可能性があります。近隣トラブルがあると、次の入居者が決まらず家賃収入の減少につながるため、慎重な入居審査を行う必要があります。
- 孤独死の危険性がある
生活保護受給者の半数以上が高齢者であり、孤独死のリスクが高いことは注意しておきましょう。孤独死が発生すると原状回復費用の負担や長期の空室などの問題が生じ、物件の価値が低下します。事故物件として認識されてしまう可能性があり、あらかじめリスク対策を講じておくことが重要です。
高齢者向けの見守りサービスを活用し、安否確認を定期的に実施することで、入居者の状況を把握できます。福祉事務所やケースワーカーと連携し、定期的な訪問を依頼することも有効な手段です。
高齢の生活保護受給者を受け入れる際は、身元保証人や緊急連絡先を明確にしておきましょう。契約時にルールを決めておくことで、万が一の事態にもスムーズに対応できます。
生活保護者向けアパートのリスク回避策4選
生活保護者向けのアパート経営は、一般的な賃貸経営とは異なる注意点があります。しかし、あらかじめリスクを理解し適切な対策を講じておくことで、不安を最小限に抑えながら安定した運用を目指せます。ここでは、実際に活用されている効果的な4つのリスク回避策を解説します。
- ケースワーカーに相談する
ケースワーカーは、生活保護受給者の支援を担当する公的な相談員であり、家賃滞納や近隣トラブルが発生した際の調整役です。ケースワーカーに相談することで、福祉事務所や支援機関と連携し、状況を改善するためのサポートを受けられます。生活保護受給者と急に連絡が取れなくなった場合でも、ケースワーカーに安否確認を依頼できます。
受給者の状況について定期的にケースワーカーと情報を共有することで、トラブルの兆候を早めに察知できます。生活保護受給者が入居する際、トラブルを未然に防ぎスムーズな管理を行うためには、ケースワーカーとの連携が不可欠です。
- 代理納付で滞納リスクを防ぐ
生活保護受給者が住宅扶助を受け取っても、家賃に充てずに別の用途に使ってしまい、滞納につながる可能性があります。自治体による代理納付制度を利用すれば、生活保護の住宅扶助が直接オーナーに支払われるため、家賃の支払い遅延や滞納の心配がありません。
代理納付はすべての自治体で実施されているわけではなく、導入状況や適用条件が異なります。物件のある自治体が代理納付制度を導入しているかを、事前に確認しておくことが重要です。生活保護者を受け入れる場合は、ケースワーカーと連携をとりながら代理納付の手続きを進めましょう。
- 孤独死保険を活用する
生活保護受給者の多くは高齢者であり、孤独死のリスクが比較的高い傾向にあります。万が一、入居者が部屋で孤独死してしまった場合、オーナーにとって大きな費用負担が発生する可能性があります。そこで、有効な手段の1つが孤独死保険への加入です。孤独死保険に加入することで、オーナーの金銭的負担を軽減できます。孤独死保険の主な補償内容は、以下の3つです。
- 原状回復費用の補償
- 家賃損失の補償
- 残置物処理費用の補償
相続人がいない場合は、オーナーがすべての費用を負担することになります。孤独死は、高齢の生活保護受給者が多いアパートでは避けて通れないリスクです。孤独死保険に加入することで、大きな金銭的負担を避けられれば、安心してアパート経営できるでしょう。
- 入居募集は早めに行う
生活保護者が入居する際には、ケースワーカーによる住宅扶助の確認や福祉事務所での審査を経る必要があります。通常の入居審査とは異なり入居手続きに時間がかかるため、早めに賃貸募集を開始することが重要です。
一般的な賃貸募集よりもターゲットが限定的なので、できるだけ広範囲に情報を発信し入居希望者を集めることがポイントです。そこで活用したいのが、ECHOESのような賃貸物件の募集サービスです。
ECHOESは各種ポータルサイトと連動しており、不動産オーナーが自ら募集情報を掲載して広く入居希望者に届けられます。不動産会社を介さずに入居者を募集できるため、スピーディーな対応が可能です。

まとめ:入居者募集を工夫すれば生活保護者向けのアパート経営が安定する
生活保護受給者の入居ニーズが増加しており、空室対策として有効な選択肢です。住宅扶助によって家賃が補助されるため、生活保護者を受け入れると家賃収入が安定しやすくアパート経営に適しています。一方で、入居までに時間がかかるケースや近隣トラブルの懸念など注意点があるため、事前に対策を講じて入居者募集することが重要です。
そこでECHOESを活用すれば、ケースワーカーとやり取りして得た生活保護者向けの条件やニーズを掲載情報に反映できます。オーナー自ら簡単に入居募集を作成できるので、物件ごとに内容を修正し思い通りの掲載が可能です。生活保護者向けのアパート経営で長期的に収益を安定させたい方は、ECHOESを無料登録してぜひお試しください。