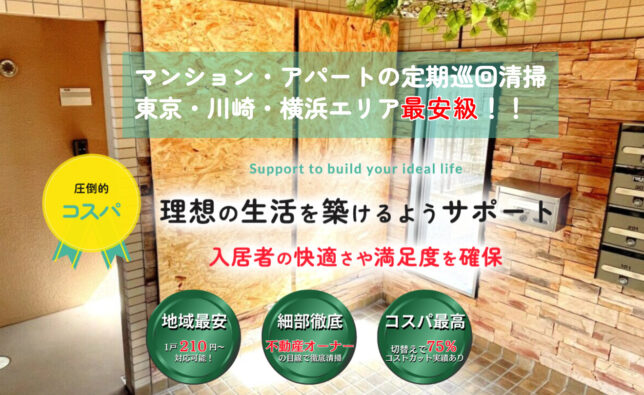登録日:2025.04.24
サラリーマンがアパート経営を行う3つのメリット!失敗例と成功のポイントも紹介

目次
「アパート経営を始めたけど収入が安定せず不安に感じている」
「借入金の返済が厳しく、アパート経営を続けて良いかわからない」
「空室を埋めるために効果的な対策はあるの?」
このようなお悩みや疑問を抱えるサラリーマンの大家さんが、いらっしゃるのではないでしょうか。アパート経営は副収入を得られる上に節税対策としても魅力的ですが、成功するにはポイントを押さえた運営が不可欠です。
本記事では、サラリーマンがアパート経営で得られるメリットと失敗例、そして成功に導くための対策を紹介します。運営コストの削減や、インターネットを活用した入居募集についても解説していますので、アパート経営に不安を感じている方はぜひ最後までご覧ください。
サラリーマンがアパート経営をして得られる3つのメリット
サラリーマンがアパート経営に取り組む理由はさまざまですが、得られるメリットは多く、正しく運用すれば安定した資産形成が期待できます。ここでは、サラリーマンがアパート経営を行うことで得られる代表的な3つのメリットについて、詳しく解説していきます。
1. 本業以外の収入が得られる
サラリーマンがアパート経営を行う大きなメリットの1つが、安定した家賃収入を得られる点です。本業に加えて毎月一定の収入が入ることで、生活に余裕が生まれ、将来に向けた資産形成にもつながります。特に教育費や老後資金など、長期的な支出への備えとして非常に有効です。
例えば、物件価格7,000万円・自己資金2割(1,400万円)、表面利回り8.6%のアパートを、融資期間25年・金利2.5%・頭金なしで購入した場合、以下のようなシミュレーションになります。
| 満室家賃収入 | 602万円 |
| 空室損失(10%) | ▲60.2万円 |
| 経費(20%) | ▲120.4万円 |
| ローン返済(借入5,600万) | ▲300.2万円 |
| 年間キャッシュフロー(税引前) | 約121.2万円 |
上記のシミュレーションでは、自己資金を2割投入しているため、ローンの返済比率が約50%に抑えられており、キャッシュフローに余裕のある安定した経営が可能です。さらに、仮に金利が1%上昇しても、年間の収支はプラスを維持できる水準となっています。
【金利3.5%(1%上昇)時のシミュレーション】
| 満室家賃収入 | 602万円 |
| 空室損失(10%) | ▲60.2万円 |
| 諸経費(20%) | ▲120.4万円 |
| ローン返済(借入5,600万) | ▲337.5万円 |
| 年間キャッシュフロー(税引) | 約83.9万円 |
ローン返済や諸経費を差し引いても、年間約83.9万円のキャッシュフローが見込めます。本業の収入を補完する手段としては十分な金額であり、着実な資産形成につながるでしょう。
2. 銀行の融資が受けやすい
サラリーマンは社会的信用が高く、安定した給与収入があるため、金融機関の融資審査に通りやすいです。アパート経営を始めるには、物件購入に多額の資金が必要となるため、この信用力は大きな強みといえるでしょう。
一般的には、年収の7〜10倍程度の融資を受けられるとされています。例えば、年収800万円の場合、8,000万円前後の借入が可能になるケースもあります。このように、会社員という立場を活かして大規模な投資に取り組める点が、サラリーマンのアパート経営における大きな魅力です。
3. 節税メリットが受けられる
サラリーマンがアパート経営を行うメリットには、税金対策がしやすい点があげられます。給与所得だけでは活用できない節税の仕組みも、不動産所得があることで利用できるようになります。中でも、アパート経営にかかるさまざまな支出を経費として計上できることは、大きな利点です。
具体的には、以下の項目が経費計上できます。
- 管理料
- 通信費
- 交通費
- 修繕費用
- 固定資産税
- ローンの金利部分
- 建物や設備の減価償却費
- 火災保険や地震保険などの保険料
これらは、確定申告の際に経費として申告することで不動産所得の金額を抑えられ、所得税や住民税の節税につながります。
またアパート経営が赤字となった場合、その赤字分は本業の給与所得と損益通算することが可能です。つまり、不動産所得で発生した赤字を給与所得から差し引くことで、全体の課税所得を下げられます。支払う税金が軽減されることで、結果的に手元に残るお金が増えるという仕組みです。
他にも、青色申告の選択により、さらなる節税効果が期待できます。青色申告で得られる代表的なメリットは、以下のとおりです。
- 青色申告特別控除(最大65万円)
- 青色事業専従者給与の経費算入
- 損失の3年間繰越控除(赤字の場合)
これらの制度を活用すれば、課税所得を抑えながら長期的な利益を確保できます。ただし、節税効果を十分に発揮するには、日々の帳簿管理や確定申告の正確さが求められます。経費の領収書をしっかり保管し、収支をきちんと記録しておくことが前提となるため、税理士などの専門家に相談しながら運営していくのも有効です。
サラリーマンのアパート経営で陥りがちな3つの失敗例
アパート経営は上手く運用すれば安定収入が得られる一方で、事前の知識や準備が不十分だと、思わぬ落とし穴にはまることもあります。特にサラリーマンは本業と並行して経営を行うため、リスクに対する判断が遅れるケースも少なくありません。
ここでは、サラリーマンがアパート経営でよく陥りがちな代表的な失敗例を3つ紹介します。それぞれの原因と対策を理解しておくことで、リスクを最小限に抑え、安定した運用につなげられるでしょう。
1. 借入金が多く返済が困難に
サラリーマンがアパート経営で陥りやすい失敗が、過剰な借入による返済の負担です。毎月の返済額が多いと、少しの空室や修繕費の発生でもキャッシュフローが赤字になってしまうリスクがあります。特に金利の変動によって返済額が増加する可能性もあり、経営が行き詰まる原因となります。
安定した経営を続けるには、家賃収入に対するローン返済額の割合、いわゆる「返済比率」を意識することが重要です。一般的には、返済比率を50%以内に抑えるのが健全とされています。例えば年間家賃収入が600万円の場合、返済額は300万円以下に設定するのが理想です。返済比率を意識した資金計画を立てることで、収支に余裕が生まれ、突発的な支出にも柔軟に対応できる経営体制を築けます。
2. 大規模修繕の資金が不足
アパートは築年数の経過とともに、外壁や屋根、防水部分などが徐々に劣化していきます。そのため、10〜15年ごとを目安に大規模修繕を行うのが一般的です。しかし、家賃収入を生活費やローン返済に充ててしまい、修繕費を十分に確保していないオーナーも少なくありません。
資金不足により必要な修繕が行えず、建物の劣化が進行した結果、家賃の減額交渉や退去につながるケースも見られます。このような事態を避けるためには、将来の修繕に備えて毎月一定額を積み立てておくことが大切です。
あわせて定期的に建物の状態を点検し、早めに劣化や不具合に気づけるようにしておきましょう。大規模修繕は単に見た目を整えるだけでなく、物件の資産価値を維持し、入居者の満足度を高めるうえでも重要な役割を果たします。
3. 管理不備による入居者満足度の低下
アパート経営において、物件の管理状況は入居者の満足度に直結します。日常的な管理が行き届いていないと、快適な暮らしが損なわれ、入居者の不満が蓄積されてしまいます。
よく見られる管理面での不備は、以下のとおりです。
- 駐輪場の乱れ
- 共用部分の清掃が不十分
- ゴミの分別・不法投棄
- 設備故障の対応が遅い
このような事態を防ぐには、信頼できる管理会社に業務を委託するか、オーナー自身が定期的に物件を巡回し、現場を確認することが大切です。入居者目線で丁寧な管理体制を整えることが、長期的な入居率の維持と安定した経営につながるでしょう。
アパート経営の成功ポイントを5つ紹介
アパート経営を安定させるには、収益を高める工夫やコストの見直し、空室対策などの基本を押さえることが重要です。本業と両立しながら効率よく運営するためにも、意識しておきたいポイントがあります。ここでは、サラリーマン大家でも実践しやすい成功のポイントを5つ紹介します。
1. 収益性アップに効果がある投資を行う
アパート経営で安定した収入を得るには、収益を最大化する工夫が欠かせません。そのためには、収益性を高めるための投資を積極的に行うことが重要です。例えば、宅配ボックスや無料インターネット設備を導入することで、入居者の利便性が向上し、競合物件との差別化が図れます。
近年ではIoT設備への関心も高まっており、スマートロックやスマート照明などを導入するオーナーも増えています。これらの設備は若年層やITリテラシーの高い入居者にとって魅力的な要素となり、物件の付加価値を高めるポイントです。設備投資の際は、費用対効果をよく見極めたうえで、ターゲット層に合った設備を導入するようにしましょう。
2. 保険を活用してリスクに備える
アパート経営には、さまざまなリスクが伴います。空室や家賃滞納だけでなく自然災害による損害、火災や入居者の孤独死といった突発的なトラブルも想定しておかなければなりません。こうしたリスクから経営を守るために、保険の活用が不可欠です。一般的な火災保険に加え、補償内容や特約を見直すことも重要です。近年においては、孤独死保険や家賃補償保険など、不動産賃貸業に特化した保険商品も登場しています。特に孤独死保険は、原状回復費用や家賃の空白期間をカバーしてくれるため、高齢者の入居を受け入れる際にも安心です。
万が一に備えて十分な補償を確保しておけば、突発的な支出による経営への打撃を最小限に抑えることができ、安定した運営につながるでしょう。
3. 運営コストを定期的に見直す
アパート経営のキャッシュフローが思うように伸びない場合、収入だけでなく支出の見直しも必要です。意外と見落とされがちなのが、運営コストの管理です。管理費、清掃費、修繕費、水道光熱費といった毎月の支出が高いと、本来手元に残るはずのお金が圧迫されてしまいます。これらの支出を定期的に見直し、必要に応じて削減を検討しましょう。
例えば、複数社からの見積もりを取り、管理会社や清掃業者の変更を検討するのもおすすめです。また共用部の照明をLEDに変更することで電気代を削減する、設備交換の頻度を見直すなど、工夫次第で支出を抑えることができます。
4. 競合調査をしっかりと行いターゲットを明確にする
アパート経営においては、常に市場の動向を把握し、競合物件と比較しながら戦略を立てることが重要です。大手ポータルサイトで周辺エリアの物件情報を定期的にチェックし、家賃相場や人気設備の傾向を掴むことで、自身の物件に不足している点や強みを明確にできます。競合調査を習慣化することで、価格設定やリフォーム内容に根拠を持たせることが可能になります。
SUUMOの「賃料・設備相場チェッカー」などのツールを活用すれば、エリア別の相場情報を手軽に確認できます。また入居者ターゲット(単身者、ファミリー、学生など)を明確にした上で、ニーズに合った設備導入や入居募集の戦略を練ることが大切です。適切なターゲット設定と競合分析を行うことで、募集の効果が格段に向上するでしょう。
5. インターネットの募集に力を入れる
入居者募集においては、いかに物件情報を多くの人に届けられるかがカギとなります。入居希望者の大半がインターネットを通じて物件を探しており、特に「SUUMO」「HOME’S」などの大手ポータルサイトの影響力は非常に大きくなっています。そのため、インターネットでの情報発信に力を入れることは、空室対策の基本といえるでしょう。
しかし、不動産会社任せでは物件が思うように掲載されていないケースもあります。そんなときは、オーナー自身がポータルサイトに掲載を依頼できる「ECHOES」を活用するのが効果的です。ECHOESを利用すれば、SUUMO・HOME’S・at homeといった大手ポータルサイトに物件情報を確実に掲載できるうえ、写真やPR文の調整も自由に行えます。
さらに、閲覧数・問合せ数などの反響データを”見える化”し、反響が伸びない原因や改善点を自動で分析してくれる機能も備えています。「成約につながる情報」をオーナー自身で作り、改善していけるのが大きな魅力です。

まとめ:ポイントを押さえてサラリーマンのアパート経営を成功させよう
サラリーマンがアパート経営で安定した収益を確保するには、収益性を高めるための投資や、無駄な支出の見直し、空室対策など、いくつかの重要なポイントを意識する必要があります。中でも空室リスクの軽減は早めに取り組むべき課題であり、入居者募集の手段によって結果が大きく左右されます。
ECHOESを活用すれば、複数の大手ポータルサイトに物件情報を確実に掲載できる上、写真やPR文の工夫によって反響をより大きく高めることも可能です。安定したキャッシュフローを実現し、将来に向けた資産形成を成功させるためにも、ECHOESを活用して安定した賃貸経営を実現しましょう。