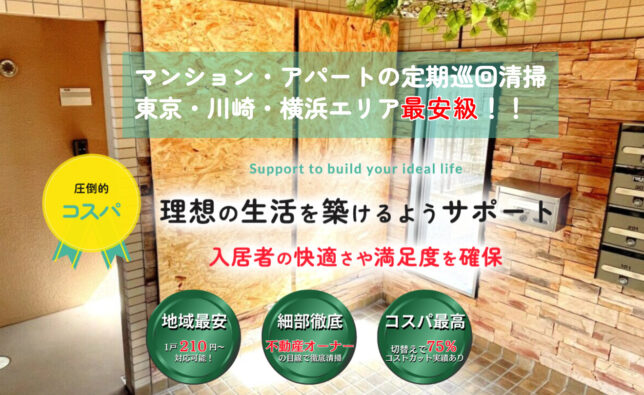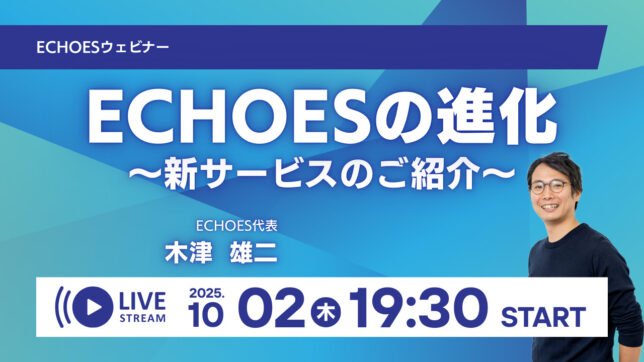登録日:2023.11.14
サラリーマン大家が成功するには?賃貸経営の基礎知識とよくある失敗

目次
サラリーマンと並行して賃貸経営を行う「サラリーマン大家」は、意外に多いということをご存じでしょうか。
国土交通省が2019年に実施した「賃貸住宅管理業務に関するアンケート調査」によると、職業が会社員であると回答した家主は全体の40%と最も多い割合を占めています。
今回は、サラリーマン大家を始めようと考えている方に向けて、賃貸経営の基礎知識やよくある失敗、そして成功のポイントについて紹介します。
サラリーマン大家のメリット
まずは、サラリーマン大家の3つのメリットについて紹介します。
安定した収入が確保できる
サラリーマン大家の場合、本業からの安定した給与が確保できるというメリットがあります。
賃貸経営では、初期費用を回収できるまで5年〜10年は見ておいた方が良いと言われています。
このように、不動産収入において短期間で利益は出にくいケースも多いため、サラリーマンとして安定した給与を確保できるのは大きな強みと言えます。
また、社会的信用も高いため、賃貸物件を取得する際の融資が受けやすくなるというメリットも。
リスクの分散ができる
本業の給与と賃貸経営による不動産収入の二本柱になるため、リスクの分散ができます。
前述したとおり、賃貸経営が軌道に乗るまでの間、企業からの給与があると安心です。
一方で、病気や怪我などで一定期間働けなくなってしまった場合も、不動産収入によって収入が確保できる可能性があります。
また、賃貸経営で赤字になった場合、給与所得と損益通算することで所得を抑え、節税することができます。
不動産所得においては、損失(赤字)を他の黒字の所得と通算して課税所得を計算することが認められています。
これにより、給与所得から源泉されている所得税の還付が受けられ、節税につながるという仕組みです。
節税になるケースも
物件の減価償却期間中は、会計上では赤字として計上することができるため、前述の損益通算を行うことでサラリーマンとしての所得を圧縮できます。
ただし、減価償却による節税は、課税所得額によっては効果が得られないこともあります。
なぜなら、物件を売却する際に結局、譲渡税を納める必要があるからです。
不動産所有時と不動産投資の売却時にかかる税率の差が生まれることで、収める税額が少なくなります。
この差が生じるボーダーラインは、課税所得額が900万円、年収にすると1200万円を超える場合です。
いずれにせよ、注意すべきポイントは「キャッシュフローがマイナスの物件を買わない」ということです。
残念ながら、「節税になる」という誘い文句で利益にならない物件を購入させるような不動産会社もあるため、収支計画をしっかり確認した上で物件の購入の可否を判断しましょう。
サラリーマン大家を始める準備

「サラリーマン大家に興味はあるものの、具体的に何から初めて良いものか迷う」という方も多いのではないでしょうか。
そこで、ここではサラリーマン大家を始める準備について解説します。
サラリーマン大家をする目的を明確にする
まずは、サラリーマン大家をする目的を明確にします。
なぜなら、目的によって賃貸経営の方針が変わるためです。
サラリーマンをしながら賃貸経営をする主な目的としては、次のようなものがあります。
- 節税のため
- 資産形成のため
- 相続税対策のため
- 相続した土地や家の活用のため
目的に合わせて、「自己資金と借入金のバランス」や「活用想定期間」「管理方式」などを決めましょう。
目的をはっきりさせないと方針が決まらないだけでなく、住宅メーカーや金融機関、不動産会社などの各相談先で、先方が売りたいと思うプランや契約に誘導されてしまうリスクもあります。
土地活用の方法を決める
土地活用といえば、マンションやアパートの賃貸経営というイメージを持たれがちですが、実は他にもさまざまな方法があります。
サラリーマン大家だけにこだわらず、最初に決めた目的に合わせて、自身に合った土地活用の方法を選択してください。
土地活用の方法として、次のようなものがあります。
住宅系(マンションやアパートの賃貸経営)
借主が住居として使用するもので、税金対策や収益の安定性から人気の高い活用方法です。
事業系
借主が事業を営む場所として使用するもので、立地によっては高い収益性が期待できます。
貸ビルやコンビニエンスストア、医療・介護施設などが該当します。
中でも介護施設は、少子高齢化が進む中で需要が伸び、注目が集まっています。
その他
駐車場やトランクルームなど、住宅系にも事業系にも属さない活用方法です。
初期費用が抑えられますが、収益はあまり大きくないのが特徴です。
事業方式を決める
土地活用の方法に続いて、事業方式も決定します。
| 方式 | 説明 |
|---|---|
| 自己建設方式 | 個人や法人が土地を所有し、自身の資金やローンを使って建物を建設する方法 |
| 事業受託方式 | デベロッパーやハウスメーカーなどに建物の開発や建設、運営などを受託する方法 |
| 等価交換方式 | デベロッパーへ土地を提供し、出資した土地の価値に応じて建物の所有権を得る方法 |
| リースバック方式 | テナント(出店希望者)から提供してもらった資金で店舗などを建築し、賃貸契約を結ぶ方法 |
| 定期借地権方式 | 土地の所有権と建物の所有権を分離し、土地を賃借する方法 |
アパート経営に関しては、自己建設方式か事業受託方式のいずれかから選びます。
自己建設方式では幅広い税金対策が可能というメリットがある一方で、手間やリスクが大きいというデメリットもあります。
事業受託方式では、賃貸経営の知識が不要というメリットがありますが、自身で事業をコントロールできないというデメリットもあります。
市場調査を行う
エリアの賃貸ニーズを把握するために、市場調査を行います。
最も手軽なのは、不動産のポータルサイトで物件情報を検索する方法です。
ポータルサイトによっては、家賃相場や付帯設備の装着率などを調べることもできます。
ただし、インターネットを使った市場調査は誰にでも簡単にできるため、仲介会社に聞く、実際にエリアへ足を運ぶなどの方法で差別化を図るのがおすすめです。
また、事業受託方式では施工会社が市場調査を行うのが一般的ですが、自身でも調査を行うことで経営判断の際に役立ちます。
サラリーマン大家では手間の少ない事業受託方式を選択する方も多いかと思いますが、ぜひ施工会社任せにせず、自身でも市場調査を行ってください。
建築会社を選ぶ
建築会社は知名度の高さや企業規模だけで選ぶのではなく、次の3つのポイントに注目して選ぶのがおすすめです。
- 現場力:現場を見学し、職人の様子や環境を確認する
- 財務状況:「住宅完成保証制度」が財務状況を判断する1つのポイント
- 提案力:目的や希望に沿った、説得力のある提案をしてくれるか
ある程度候補を絞ったら、候補に残った全ての企業から見積もりを取って比較を行います。
その際、総工事費だけでなく、必ず内訳明細まで確認しましょう。
資金計画を立て、資金を調達する
建築会社から、基本設計や見積もりを元にした収支計画を提案してもらいます。
収入面では家賃の下落や空室率など、支出面では金利上昇リスクや維持・修繕費などを考慮して、現実的な計画が立てられているかを確認してください。
アパート経営の場合、最初に必要な資金は一般的に物件価格の1〜3割程度と言われています。
資金調達の方法については、アパートローンを借りる方がほとんどです。
アパート経営や初期費用については、こちらの記事を参考にしてください。
>>アパート経営の初期費用は?内訳とシミュレーションで必要な自己資産を確認
サラリーマン大家の実務とは?

サラリーマン大家を始めるにあたってハードルの1つとなるのが、本業と両立できるかどうかではないでしょうか。
サラリーマン大家の実務を確認し、本業との両立が可能かを判断してください。
賃貸経営の実務は、大きく分けて次の2種類です。
入居者管理
入居者管理は、入居者をマネジメントする仕事です。
具体的には、入居者募集や契約管理、家賃収納、トラブル対応などが挙げられます。
入居者管理は入居者の満足度に影響し、空室対策にもなるため、特に重要な実務と言えます。
- 入居者募集:物件情報の掲載や、入居希望者の信頼性・支払い能力の確認
- 契約管理:賃貸契約の締結や更新、解除の手続き
- 家賃収納:家賃の集金。滞納がある場合は督促も行う
- トラブル対応:入居者からのトラブル相談やクレームに対応する
建物管理
建物管理は、建物のメンテナンスや修繕などを行い、入居者の住環境を整える仕事です。
共用部の清掃や点検、故障した設備の修繕、大規模修繕など多岐にわたります。
建物管理により物件価値を保つのも、空室対策の一環です。
- 共用部の管理:清掃や電球交換などの保守点検を行う
- 設備の修繕:各部屋や外回りの設備の不具合を修理、または業者を手配する
- 大規模修繕:老朽化した建物の大規模修繕を立案、実施する
以上のように、賃貸経営の業務は非常に幅広く、サラリーマン大家の場合すべて自分で行うには限界があります。
そこで、業務を管理会社へ委託する「委託管理」を選択するサラリーマン大家が多いです。
サラリーマン大家の失敗事例

サラリーマン大家を始めてみたものの、失敗してしまったというケースも見受けられます。
ここからは、サラリーマン大家にありがちな失敗事例を3つ紹介します。
物件選びのミス
サラリーマン大家を始める際に物件選びに失敗してしまい、思うような利益が出なかったというケースです。
利回りだけを見て判断してしまった
物件選びの際、利回りを1つの指標にする方も多いと思いますが、広告に表記されている利回りは空室や管理費、固定資産税などを考慮していないことがほとんどです。
例えば広告では利回り10%の物件が散見されますが、実際は家賃収入を物件価額で割っただけの「表面利回り」である可能性が高いです。
利回りだけを見て物件を選ぶと、想定していた収入が得られず赤字になってしまうなどの失敗につながりかねません。
利回りについて詳しく知りたい方は、こちらの記事もおすすめです。
>>【徹底解説】アパート経営の利回りの目安と最低ライン、計算方法は?
管理費や維持費がかさんだ
初期費用を抑えようと中古物件を購入したところ、劣化が早く管理費や維持費がかさんで、かえって高くついてしまったという失敗もあります。
中古物件の購入がNGというわけではありませんが、購入する際はリフォーム費なども考慮し、しっかりシミュレーションを行いましょう。
家賃収入があまり得られなかった
ワンルームマンションは比較的少額で購入することができますが、管理費や修繕積立金がかかる上に、他の間取りに比べて家賃収入も少ないのが一般的です。
その他、近隣の学校や工場がなくなり退去者が多く出るなどが原因で、想定していた家賃収入が得られなかったというケースもあります。
以上が、物件選びのミスの事例です。
いずれも利回りや物件価格だけで購入を判断したことが原因のため、物件選びの際はキャッシュフローを綿密にシミュレーションすることが大切です。
すべて自主管理で行う
「サラリーマン大家の実務とは?」の項目でも解説した通り、サラリーマン大家の業務は非常に多いため、管理会社へ委託するサラリーマン大家がほとんどです。
委託管理の場合は一般的に、家賃収入の5%〜10%ほどの管理費がかかります。
管理費を削るためにすべて自主管理で行うと、失敗につながりかねません。
本業が忙しく、清掃がおろそかになれば、入居者の満足度が下がり空室リスクにつながるかもしれません。
また、クレームやトラブル対応もスピードが命なので、深夜早朝など時間を問わず対応するには自主管理では限界があります。
なお、既出の「賃貸住宅管理業務に関するアンケート調査」では、「業者に任せず、全て自ら管理している」と回答した家主は全体の2割程度でした。
このように、サラリーマン大家に限らずほとんどの家主が、委託管理を選択していることが分かります。
確定申告の失敗
サラリーマン大家の場合、確定申告にあまり馴染みがないために申告を忘れてしまう傾向にあります。
給与以外で20万円以上の所得を得た場合は、必ず確定申告を行いましょう。
赤字になってしまった場合、確定申告は必要ないと思われがちですが、冒頭で解説した損益通算によって節税が可能です。
サラリーマン大家として成功するためのポイント

サラリーマン大家として成功するためには、次の3つのポイントを意識すると良いでしょう。
自主管理とアウトソーシングのバランスを取る
「サラリーマン大家の失敗事例」でも解説した通り、賃貸経営のすべてを自主管理で行うのは非常に大きな負担になります。
とはいえ、すべてを外注するとコストがかさみ、収益を圧迫することもあります。
そこでおすすめなのが、「自分でできる範囲は自分で行い、難しい部分だけをアウトソースする」バランス型の管理です。
中でも、入居者募集は比較的取り組みやすく、かつ成果に直結する業務のひとつです。
例えば、物件の魅力を一番よく知っているのはオーナー自身だからこそ、掲載情報を自分で作成することで、より効果的なアピールが可能になります。
実際に近年では、大家さん自身で募集活動を行うケースが徐々に増えており、「自分で掲載したほうが早く決まる」「情報の自由度が高い」などの声も多く聞かれています。
そんな“新しい募集スタイル”をサポートしてくれるのが、賃貸募集支援サービス「ECHOES(エコーズ)」です。
ECHOESなら、SUUMO・HOME'S・at homeといった主要ポータルサイトに、オーナー自身が作成した情報をそのまま一括掲載できます。
作成はお持ちの募集図面をアップロードするだけでOK。ターゲットに合わせて情報を自由に編集できるので、より伝わる訴求が実現します。
さらに、反響データ(閲覧数・問い合わせ件数・内見結果など)も可視化できるため、「どこを改善すれば入居が決まりやすいか」を数値で把握し、スピーディに対策を講じることも可能です。
手間を最小限にしつつ、成約率を高める募集を自分の手でコントロールできる、それがECHOESの大きな強みです。
まずは比較的手軽な入居者募集から、自主管理にチャレンジしてみませんか?
その際は、ECHOESの導入をぜひご検討ください。

事前にリスクを知り、備える
賃貸経営で起こり得るリスクを知り、事前に備えることで失敗を防ぐことができます。
最も多いのは、空室リスクです。
安定した家賃収入のためにも、賃貸経営において空室対策は非常に重要と言えます。
空室対策としては、ターゲットや募集情報の見直し、設備の見直しなどが挙げられます。
詳しい空室対策について知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
>>アパート・マンションの空室対策10選。やってはいけない方法や実施のタイミングも
また、空室リスク以外にも起こり得るリスクについては、次の記事で解説しています。
>>アパート経営の失敗事例10選から学ぶリスク回避の方法とは
経費を上手く計上する
確定申告の際に、できるだけ数字上の収入を少なく、支出を多く計上することで不動産所得にかかる税金を少なくできます。
1つは、減価償却をとる方法です。
賃貸物件を取得したときは、全額まとめて必要経費とするのではなく、建物の法定耐用年数で割った額を必要経費として計上していきます。
もう1つは、支出をできるだけ経費として計上する方法です。
賃貸経営にかかるコストの中には、保険料や管理費、ローンの金利など、経費として計上できるものがいくつかあります。
経費にあたる項目を確認し、申告漏れがないようにすると節税につながります。
サラリーマン大家を法人化するタイミングは?

サラリーマン大家が軌道に乗ってくると、法人化を検討する方も多いです。
税金や所得の金額から法人化の可否を判断する場合、次の2つが目安となります。
- 200万円以上税金を納めている
- 総所得金額が1,000万円を超える
ただし、法人化によって一定のコストもかかるため、必ずしも法人化によって利益が増えるとは限りません。
詳しくは、次の記事でご確認ください。
>>アパート経営の法人化のタイミングに迷ったら。メリットやコスト、手続きを解説
まとめ:サラリーマン大家は自主管理と外注のバランスが大切
サラリーマンとして働きながら賃貸経営を行うには、すべてを自分で抱え込まず、上手に外部の力を借りることが大切です。
信頼できる不動産会社や管理会社と連携しながら、自分で対応できる部分は自主管理でコストを抑える――このバランス感覚が、長期的な成功につながります。
中でも、入居者募集は比較的取り組みやすく、自分の力で収益性を高められる業務のひとつです。
実際、オーナー自身で募集活動を行うケースも増えており、空室対策の第一歩として注目されています。
まずは、比較的手軽にできる入居者募集から、自主管理にチャレンジしてみてはいかがでしょうか?
その際は、賃貸募集支援サービス「ECHOES(エコーズ)」の活用がおすすめです。
>>ECHOES